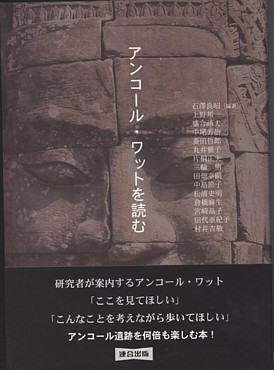 「アンコール・ワットへ出かけるならここを見てほしい」「こんなことを考えながら歩いてほしい」――第一線の研究者たちがアンコール・ワットと周辺の遺跡を案内する。遺跡に残るいろいろな痕跡、見えないところの話、埋納仏像発見顛末記、往時のアンコール・ワットの姿、などアンコール遺跡を何倍も楽しむためのぜいたくな本。A5判424ページ。
「アンコール・ワットへ出かけるならここを見てほしい」「こんなことを考えながら歩いてほしい」――第一線の研究者たちがアンコール・ワットと周辺の遺跡を案内する。遺跡に残るいろいろな痕跡、見えないところの話、埋納仏像発見顛末記、往時のアンコール・ワットの姿、などアンコール遺跡を何倍も楽しむためのぜいたくな本。A5判424ページ。
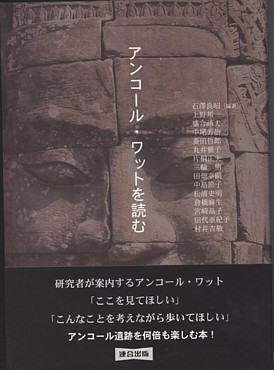 「アンコール・ワットへ出かけるならここを見てほしい」「こんなことを考えながら歩いてほしい」――第一線の研究者たちがアンコール・ワットと周辺の遺跡を案内する。遺跡に残るいろいろな痕跡、見えないところの話、埋納仏像発見顛末記、往時のアンコール・ワットの姿、などアンコール遺跡を何倍も楽しむためのぜいたくな本。A5判424ページ。
「アンコール・ワットへ出かけるならここを見てほしい」「こんなことを考えながら歩いてほしい」――第一線の研究者たちがアンコール・ワットと周辺の遺跡を案内する。遺跡に残るいろいろな痕跡、見えないところの話、埋納仏像発見顛末記、往時のアンコール・ワットの姿、などアンコール遺跡を何倍も楽しむためのぜいたくな本。A5判424ページ。
カンボジア全図・アンコール・ワットと周辺の遺跡地図
カンボジア王統の系譜
アンコール王国遺跡一覧
第二章 碑文・王朝年代記が語る歴史の実相 ……石澤良昭
第三章 遺跡に残る痕跡が語る ……上 野邦一
第四章 遺跡の悲鳴を聴く ……盛合禧夫
第五章 土を読む―バンテアイ・クデイ寺院跡の発掘調査から― ……中尾芳治
第六章 遺跡の図面を読み解く ……菱田哲郎
第七章 仏像埋納坑を読む ……丸井雅子
第八章 アンコール・ワットの建築技術と修復 ……片桐正夫
第九章 石を読む―アンコール・ワット西参道から― ……三輪 悟
第十章 アンコール王朝と陶器 ……田畑幸嗣
第十一章 ヨーロッパからアンコールを読む ……中島節子
第十二章 『真臘風土記』を読む ……松浦史明
第十三章 宇宙観を読む ……倉橋麻生
第十四章 バイヨン様式の観世音菩薩像を読む ……宮崎晶子
第十五章 アンコール遺跡と地域社会 ……田代亜紀子
終章 マス・ツーリズムとエコ・ツーリズム ……村井吉敬
索引
アンコール文明は、インドシナ半島中央部のちょうど現在のカンボジアを中心とした大扇状地アンコール地方に集中して約六百年間にわたり展開した文明である。アンコールとは、「都城」を意味する梵語「ナガラ」がクメール語化して発音されたものである。
本書、『アンコール・ワットを読む』はカンボジアの現地で遺跡の調査・修復に携わってきた研究者が、それぞれの研究の立場から、人々を魅了してやまないアンコール遺跡のなぞに迫ったものである。アンコール遺跡を体験した人にとって、そして何よりもこれから訪れようとする人にとって、本書がこの類まれな人類の遺産をより深く味わうために役立つのであれば、編者としてこれにまさる喜びはない。
石 澤 良 昭
即位した王は、自らの権威を示すため新しい都城・寺院・王宮の三点セットの建設に着手した。だからアンコール地方には結果として未完成を含めたくさんの遺跡や遺趾が残っている。約六百年間もアンコールの地に居座り続けた理由は、インドから入ってきた宇宙観にあった。つまり神々が住むと言われる聖山須弥山をプノン・クレーン高丘に、聖河ガンガーをシェムリアップ川に、聖都アヨーディヤーをアンコール都城になぞらえ見立てていた。当時のクメールの人たちはこれら聖なる神の世界を構成する大道具がこのアンコールの地に揃っていると考えていたからであった。
アンコール時代には「施療院」と「灯明のある家」が各地に設置されていた。国内各地は道路や橋によってアンコール都城とつながり、頻繁な往来があった。A・マルローはその小説『王道』(一九三〇年)の中で、密林内を縦横に王道が走っていたと書いた。最近の調査で、こうした王道なる道路網は実在していたことが判明した。アンコール朝最盛期の十二世紀には、王道が現在の東南アジア大陸部各地に通じていた。
現在カンボジアの密林の奥地に放置されたままの五ヵ所の大遺跡はかつての五大地方都市であり、王道でつながっていた。その五大遺跡のうち、七世紀の都城サンボール・プレイ・クックはアンコールから約一四〇キロ離れたところにあり、十世紀前半の都城コー・ケーは約九五キロ離れたところにある。他の三つは、アンコールから四〇キロ離れたベン・メリア寺院、一二五キロ離れたバンテアイ・チュマール寺院、コンポン・スヴァイの大プリヤ・カーン寺院である。どれも規模としてはアンコール・ワット級の大きさであり、大プリヤ・カーンはアンコール・ワットの四・七倍の大伽藍である。
アンコール都城の繁栄の裏付けとなる食糧の米の生産について、一九七九年にG・ グロリエが「アンコール水利都市」論を提起した。当時のアンコール水利都市全体で一二万六千トンの籾米が収穫され、周辺に人口約六十万人を養うことができたという。アンコール地方の地形は北から南にわずかに傾斜している。乾ききった季節にバライ(貯水池)の堤を切ると、傾斜に沿って水はゆっくり下方へ流れ、さらに下の土手を切れば、水はさらに落ちる。土手に囲まれた大区画を一枚の田として田植えを行なう。このような「田越し灌漑」仮説は、JICA(国際協力機構)作成の五千分の一地形図に基づき検討されている。
アンコール時代の寺院は、その壁面という壁面が全て壮麗で秀美な装飾彫刻で埋め尽くされ、今でも建物全体がちょうどレースのヴェールで覆われているような錯覚を覚える。つまり寺院や祠堂が基壇から塔頂まで、どこの石の上にも、また塔身や屋蓋のどの部分にも浮彫りと細かい模様が施されているのである。その精緻な模様装飾と浮彫りはまさしく満艦飾であり、圧巻である。これらの建築装飾が彫工・工匠・図工・漆工・仏師などの手仕事であったことは、本当に驚嘆に値する。
これらの装飾模様と彫刻などは、彫工や図工たちの自由奔放な発想によるものではなく、輪廻転生の宗教観に立脚したものである。多彩な模様は、自然と人間が一体という世界観、生きとし生けるものすべてどの動物も生死を繰り返す一つの姿に過ぎず、森羅万象は永遠に転生し続けるという法則に基づいているのである。小人物像は他の模様と重複凝集し、連続模様と一体になって描かれていることが特徴である。ここにカンボジア人の美意識なるものの源がある。この美意識は、民族の身体の中に染み込み、醸成され、血の中に入っている。
栄華を誇ったアンコール文明が衰亡した原因は、一つに特定することはできないだろう。一三五三年以降、王の名前すら分からないほど国内は混乱していた。同じ頃、隣国アユタヤ軍の攻撃があったようであり、王都は回復できないほど破壊され、多くの人が捕虜として連行された。一四三一年頃、再びアユタヤ軍の総攻撃を受け、アンコールは完全に廃都となった。
そのような外部要因だけでなく、王位継承権をめぐる国内分裂による内戦、ヒンドゥー教・大乗仏教から上座仏教への変更などといった宗教思想の混乱、アンコールの社会生活を支える水利施設が機能しなくなったこともあげることができる。いずれにしろ、あれほどまでに高い水準の文明を築き上げた人々にも、防ぎようのないものがあるということである。人間の行なうことに、完全で永久なものはないのである。