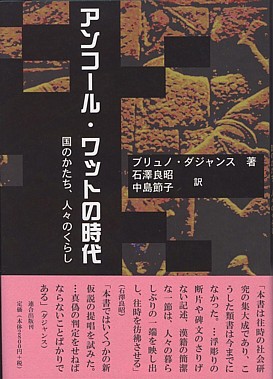 フランスの著名な歴史学者が碑文からわかること、浮彫りからわかることを紹介し、石澤良昭上智大学学長が中国史料と最新の研究について校注を附した、アンコール・ワット研究の金字塔。「歴史」「都城と王国」「政治・社会組織」「経済活動」「時間と空間」「宗教」「文学」「くらし」など
フランスの著名な歴史学者が碑文からわかること、浮彫りからわかることを紹介し、石澤良昭上智大学学長が中国史料と最新の研究について校注を附した、アンコール・ワット研究の金字塔。「歴史」「都城と王国」「政治・社会組織」「経済活動」「時間と空間」「宗教」「文学」「くらし」など
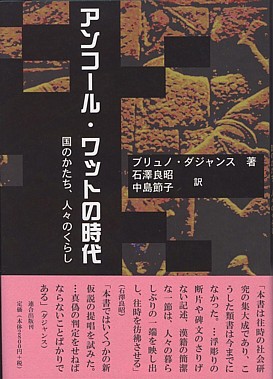 フランスの著名な歴史学者が碑文からわかること、浮彫りからわかることを紹介し、石澤良昭上智大学学長が中国史料と最新の研究について校注を附した、アンコール・ワット研究の金字塔。「歴史」「都城と王国」「政治・社会組織」「経済活動」「時間と空間」「宗教」「文学」「くらし」など
フランスの著名な歴史学者が碑文からわかること、浮彫りからわかることを紹介し、石澤良昭上智大学学長が中国史料と最新の研究について校注を附した、アンコール・ワット研究の金字塔。「歴史」「都城と王国」「政治・社会組織」「経済活動」「時間と空間」「宗教」「文学」「くらし」など
――――――――――――――――――
第二部 クメール人の生活
――――――――――――――――――
第五章 時間と空間の展開
暦法と年号
宗教行事と年号
生活時間
祭礼の暦
方位空間
寺院空間
農業空間
空間の構成
第六章 宗教と宇宙の支配者
ヒンドゥー教
仏教
シヴァ派と大乗仏教の相克
インドの神々の受容
シヴァ神と周辺の神々
ヴィシュヌ神とその化身
ヒンドゥー教の陪神・護世神・女神
仏陀――大乗仏教と上座仏教
観世音菩薩
眷属たち
乗用聖獣
特定の人物像が安置された寺院
四面仏尊顔は国土守護の神か
日常生活の中の宗教
修行者と苦行僧
第七章 文学
カンボジアにおけるサンスクリット語文学
作者と作品
クメール語文学の誕生
第八章 美術
寺院と都市計画
浮彫り図像と村人たち
インド寺院からクメール版寺院へ
多彩な肖像彫刻
建築装飾と身舎
アンコール美術の編年と様式
インド美術からのクメール様式発展期(六〜九世紀)
アンコール美術の新発展(九〜十一世紀)
アンコール美術の隆盛(十一世紀末〜十二世紀前半)
アンコール美術の末期
伝統音楽と古典舞踊
第九章 クメール人の日常生活
誕生から青年期へ
結婚、家庭と女性
老いと死
家屋と生活
料理と食事
都城と王の行幸
森の中の生活
余暇と娯楽
病気と医療
施療院
医師と薬石
貝葉写本の教育
教育
衣服と身体装飾
金銀細工と装飾品
【附録】
アンコール王朝歴代国王および主要人物の履歴
【索引】 【日本語参考文献】
カンボジア研究は、やっと一五○年を迎える比較的若い学問領域であり、西欧人にとっては、既に千年を越えている身近な存在の地中海文明の研究とは大きく異なる。しかし、遺跡現場での調査研究活動と主として研究室で構築された諸成果を組み合わせることで、一九七○年代の初めまで停滞していた研究の遅れはほぼ解消されたと言える。重厚な研究成果に基づき諸仮説がすでに唱えられてはいた。それが、G・セデスやJ・ ボワスリエの金字塔的な成果であった。その後、[一九七○年からの内戦で]一五[二五]年にわたり現地との接触が断たれ、その間に[フランス極東学院のカンボジア]研究チームが解散したり、若いクメール人研究者が多数失われてしまったりした。こうした試練を経て、カンボジア研究は再出発することになったのである。一九八○年代末を皮切りに、研究者の世代交代、研究方法論の一新、研究チームの再編成や課題プロジェクトの多様化、研究領域の細分化、これまでに存在しなかった新技術の活用によるあらゆる領域での研究成果の急増などにより、昨今は過去のみならず最近の成果でさえも問い直されているのである。
フランスの作家で文化大臣までつとめたアンドレ・マルロー(一九〇一〜一九七六)は、一九三〇年に上海で小説『王道』(La voie royale)を発表した。マルローはその小説の中でアンコール王朝時代の幹線道「王道」が密林の中を縦横に走り、村人たちが往きかっていたと言及した。一九九〇年代になってその往時の王道が次々と発見され、東南アジア大陸部各地へ通じていたことが判明した。次頁に掲げるスピアン・プラトス大橋は現在カンボジア中部にあって、約千年近くにわたり使われており、いまもその橋の上を自動車が走っている。
本書では、仮説の細部にまで踏み込むことはできないので、少しばかり向こう見ずはであるが、史実と認められている範囲内でいくつかの新仮説の提唱を試みた。そのため読者諸賢の疑念を招くかもしれないが、これが各方面から検証されることを願っている。いずれにせよ、真偽の判定をせねばならないことばかりである。例えば遺跡の建設年代であるが、建設あるいは完成を祝う碑文に記された年代には問題があり、どれを採るかがまず問題である。しばしば建設の開始を前王の時代に位置づける仮説についても、カンボジアでは王権が優位にあるとの観点に立てば、当然そこに新たな疑問が起こってくる。現在取り沙汰されている問題点としては、クメール人の国の歴史が始まった初期の頃の政治的枠組み、時代ごとの権力の集権と分権、さらにはB・Ph・ グロリエが提起した「水利都市論」の再検討などがある。クメールの職称と階層制度、その歴史的変遷も、まだ仮説の段階である。現在進行中の現地発掘調査には多くの期待がかかっている。それはアンコール・トムやその他の考古発掘調査、最盛期の森林区画調査などであり、とりわけ古代カンボジアの経済、生活の枠組み、先史時代と歴史時代の相関関係の解明に関心が寄せられている。碑文に関しては、対象となる現場が多くあり、なかなか手応えのある研究が出ている。最近であるが、シヴァ派の経典について、碑文の中にその言及があることが確認された。九世紀にデーヴァラージャ[神王]がサンスクリット語化されたが、その[ヒンドゥー教神学上の]背景を十三世紀の宗教対立の問題と共に検証していきたい。さらに、有名な碑文が再出版され、翻訳が進めば、あらゆる分野において組織だった研究の展開ができる。碑文にはその時々の経済活動の数量的な側面や称号および肩書などについての言及があり、美術史や既に指摘した編年学の問題などの再考察を促している。
本書の願いは、まずは既定の仮説の整理と理解に資することであり、さらに、読者諸賢の関心を、最近の研究の成果とそこから出てくる種々の問題にまで引き付けられるとしたなら、その目的は十分に達成されよう。
ブリュノ・ダジャンス
訳者まえがき
この巨大な石橋はアンコール王朝時代に造営されたが、これを造った王朝はどんな政治を執り行い、どんな社会が機能していたのか、その最盛期の十二世紀から十三世紀にかけて東南アジア大陸部では「すべての道はアンコール」都城へと通じていた。
アンコール・ワットをはじめとする石造遺跡群は並外れてその規模が大きく、広範囲にわたっており、たくさんの寺院や祠堂、貯水池などがアンコール地域に密集している。十九世紀中ごろアンコール遺跡群が再発見され知れわたると、だれもが、この巨大遺跡は何なんだと疑問を投げかけた。そして、遺跡の謎解きが始まったのである。伝説や仮説、臆説が一人歩きして世論を盛り上げた。
それに加えて、遺跡に安置されていた優美な彫像および繊細な浮彫りや装飾が美術鑑賞の対象として多くの人の心をとらえ、個人的な思い入れを増幅させたようである。どちらかというと王朝研究は当初、異端邪説の修正や寺院の建立年代の誤り修正に追われていたと言ってよい。紆余曲折を経て、一九三〇年代に碑刻文史料が出そろい、ようやく遺跡の本格的な科学的解明が始まった。
その後カンボジアは、一九五三年に独立を果たし、国王が先頭に立って政治を行ない、世界の注目を集めた。やがて東西冷戦に巻き込まれ、やがて恐怖政治と内戦の時代に突入した。
一方この間、碑文の正確な解読、漢籍史料の再検討、考古発掘、保存修復活動等による専門的研究が海外において着実に積み上げられてきた。しかし、約三十年続いた内戦は研究活動の空白期間をつくり、多くのカンボジア人研究者を失い、カンボジア和平成立の一九九三年はまさにゼロからの出発であった。
再度本題に戻る。この大きな石造橋梁の建設を可能にしたアンコール王朝とはどんな国家だったのか、そのほとばしるエネルギーの実体は何であったのか。カンボジア版ヒンドゥー教と仏教はどんな新精神価値体系を創り出したのか。巨大建造物造営を可能にした根本思想は何だったのか。
――本書はそうした数多くの疑問に答えると同時に、より深い歴史理解のための史実を例示し一つずつ丁寧に説明している。その中で、これまでの諸説についての史料批判を加え、それに替わるいくつかの仮説や答えを用意している。本書はその意味においてこれまでの遺跡別解説と異なり往時の社会研究の集大成であり、こうした類書は今までになかったと言ってよい。
何より本書は、アンコール王朝の歴史を学ぶことの楽しさ、いうなれば謎解き的解明手法も手伝って読者をわくわくさせてくれるに違いない。浮彫りの断片や碑文のさりげない記述、漢籍の簡潔な一節は、人々の暮らしぶりの一端を映し出し、往時を彷彿させる。
原書のタイトルは『クメール』(Les Khmers)であるが、ここで主として取り扱っているのはアンコール王朝時代の社会と文化、日常生活であることから表記の邦題とした。
B・ダジャンス教授は長年にわたりパリ第三大学のインド文明学科を担当され、フランス極東学院ポンディシェリー校を中心に活躍してこられた。教授の主要研究業績としては『マヤマタ書』(インド建築サンスクリット語テキスト)校注付訳書がある。すでに日本で翻訳された著作としては『アンコール・ワット――密林に消えた文明を求めて』(創元社、一九九五年)があり、発刊以来高い評価を受け版をかさねている。
なお、文中の[ ]で表わした箇所は訳注である。歴史背景を理解するための一助にしていただきたい。
本書の訳出に着手してから三年余りの歳月が過ぎてしまった。この間、多くの方々に問い合わせをしたり、ご教示いただいた。特に浄書と校正にあたっては谷口聡美さんに、校閲と史料点検では松浦史明氏に大変お世話になった。そして訳稿を忍耐強く待ってくださった連合出版の八尾正博氏にも厚くお礼申し上げたい。
二〇〇八年一月 石 澤 良 昭
(上智大学学長)